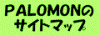2016年02月09日
三ツ石山(松川温泉から)-山スキー②

日程:2016年2月6日(土) 日帰り
天候:曇/晴
 /
/
▲三ツ石山(みついしやま)
標高:1,466m
岩手県(雫石町・八幡平市)
東北百名山
(地理院地図はこちら)
▲覘標の台(てんぴょうのだい)
標高:1,447.9m
岩手県(雫石町・八幡平市)
三ツ石三角点
<ルート>
◎源太ヶ岳登山口(松川温泉)~奥産道~▲三ツ石山
~▲覘標の台~奥産道~源太ヶ岳登山口
<関連記事>
2015年09月05日 源太ヶ岳~三ツ石山-縦走登山
2015年01月15日 源太ヶ岳-山スキー
2014年07月14日 三ツ石山-登山
2014年01月18日 三ツ石山-山スキー
2013年03月03日 源太ヶ岳-山スキー
2010年04月04日 三ツ石山-山スキー
2009年10月04日 三ツ石山-登山
<その1からの続き>
▲7:45 登山口 ~ ▲8:15 小畚橋 ~ ▲8:25 奥産道P ~ ▲9:20 1,260P ~ ▲10:45 三ツ石山





三ツ石山の山頂でもうちょっと待ってみたかったが...
風に悩まされ下山を決意。
しかし、天気は回復してきた!
▲11:10 三ツ石山 下山
徐々に晴れつつある三ツ石山周辺。
遠くの景色がはっきりしてきた。
正面には三角点ピークの覘標の台。更に奥のピークは小畚岳と思われる。

そして青空も広がりモノクロームな世界から一転する。

景色は良くなってきた。
しかし風がとても強い...顔が痛い...
この写真から強風は読み取れないか??

そして樹氷。
八幡平のモンスターに比べればボリューム感がないが、それでも立派な樹氷である。

今年は雪不足ではあるが、八幡平の樹氷はそろそろ出来上がっているのか?
振り返れば三ツ石山の山頂も青空の下。

おっ!?
誰かが登頂した!
肉眼で3~4人に見えた。
カメラのズームを目一杯にしてその姿を写真に残した。

きっとタラさん達だろうと。
山頂でもうちょっと待つべきだったな...
ちょっと手を振ってみたが...
視力が低下した私の肉眼には黒い点にしか見えなかった。
戻ることなく、覘標の台を目指す。

平原に降り立つ。
この辺りが三ツ沼の様だ。
(秋の三ツ沼の記事はこちら)

樹氷の背景に岩手山。
残念ながら岩手山の山頂までは見えなかった。


何度も三ツ石山のピークを振り返る。

んっ?
誰かが三ツ石山から降りて来たようだ。
タラさんかな?
三ツ石山から降りてきたのは1名だけの様に見えた。
三ツ石山から大分遠ざかって来た。
風は強いが、絶景を堪能しながら気持ちよく歩ける。

丘に上がって辺りを見廻す。

▲11:55 覘標の台
この読みは「てんぴょうのだい」。
覘標とは陸地測量の際、選定地点に遠くから見えるように設ける目標。
3本または4本の木材を角錐状に合わせたもの。
その下に三角点を埋める。
ここは三等三角点(点名:三ツ石)
標高は1,447.94mの場所だ。
運良く、積雪から三角点の頭が出ていた。
今年初の三角点タッチ!



さて、ここでシールを外すことにする。
シールを剥がす時に気づいた...
シール後方のエッジ部分が1cmほど切れている。
きっと石か木を踏んだのかと?
シール(Gecko)を修理してからトラブル続きだ...
▲12:05 覘標の台 下山
さて、ここからは滑走となる。
元来たルートへ戻るように、東斜面を滑走した。
東斜面は滑り易い雪質だった。

南方面のその奥に三ツ石山頂を眺める。

滑走に適したオープンバーンはあっという間に終了。

その後は暫く平坦な道のりである。
シールを貼るまでもないが、少々の登りもあり...
「少々」でもシール無しの登りは体力を使う。

緩斜面でもフワフワの雪は滑りが楽しい。
アオトドを掻い潜って滑る。

ある程度滑り、登りのトレースへと合流した。
さて、登り時に「滑りが楽しそう~」と思っていたあの斜面へ戻って来た。
風の流れで創られた雪の波を利用して相方は飛ぶ。


上質パウダー。

イイ斜面はあっという間に滑り降りてしまう。
ここを下りると、小ピークまでは短い区間だが登りになる。
シールを貼って登ることにした。
服の中にシールを入れておいたので、着いた粉雪も融けて貼り付きが良かった。
少々登っては小ピークで再びシールを剥がす。
ここからはもうシールは要らない。
奥産道の上部の樹林へ戻って来た。
針葉樹林から変わって斜面には藪もあり...
樹林密度の低い場所を選んで斜面滑走!


滑りは安全第一で!


▲13:00 奥産道
無事、奥産道へと戻って来た。
そのまま、奥産道を滑って下る。
せっかくここまで来たので、ちょっと上のトラス橋へも行ってみるんだったな...
下りの奥産道も平らなだけにちょっと歩きが面倒だな。(小畚橋の辺り)
それでも15分程度で閉鎖ゲートまで戻ることが出来た。

▲13:15 登山口
無事下山、お疲れさんでした。
今日の奥産道は我々2人のトレースのみだった。
源太ヶ岳へもここからは誰も入らなかったようだな。
先ずは今回のトレースを振り返る。

源太ヶ岳の樹林内と異なり、滑りに適した斜面は長くは続かない。
ところどころに平坦な場所が交じるといった感じである。
それでも初めてのルート。
景色が新鮮で、ハイクも飽きずに楽しむことが出来た。
何と言っても樹林外で天気が回復してくれたことが幸い。
厳冬期の三ツ石山であの絶景を味わえたことは嬉しい限り。
では、また山で!
(完)

徐々に晴れつつある三ツ石山周辺。
遠くの景色がはっきりしてきた。
正面には三角点ピークの覘標の台。更に奥のピークは小畚岳と思われる。

そして青空も広がりモノクロームな世界から一転する。

景色は良くなってきた。
しかし風がとても強い...顔が痛い...
この写真から強風は読み取れないか??

そして樹氷。
八幡平のモンスターに比べればボリューム感がないが、それでも立派な樹氷である。

今年は雪不足ではあるが、八幡平の樹氷はそろそろ出来上がっているのか?
振り返れば三ツ石山の山頂も青空の下。

おっ!?
誰かが登頂した!
肉眼で3~4人に見えた。
カメラのズームを目一杯にしてその姿を写真に残した。

きっとタラさん達だろうと。
山頂でもうちょっと待つべきだったな...
ちょっと手を振ってみたが...
視力が低下した私の肉眼には黒い点にしか見えなかった。
戻ることなく、覘標の台を目指す。

平原に降り立つ。
この辺りが三ツ沼の様だ。
(秋の三ツ沼の記事はこちら)

樹氷の背景に岩手山。
残念ながら岩手山の山頂までは見えなかった。


何度も三ツ石山のピークを振り返る。

んっ?
誰かが三ツ石山から降りて来たようだ。
タラさんかな?
三ツ石山から降りてきたのは1名だけの様に見えた。
三ツ石山から大分遠ざかって来た。
風は強いが、絶景を堪能しながら気持ちよく歩ける。

丘に上がって辺りを見廻す。

▲11:55 覘標の台
この読みは「てんぴょうのだい」。
覘標とは陸地測量の際、選定地点に遠くから見えるように設ける目標。
3本または4本の木材を角錐状に合わせたもの。
その下に三角点を埋める。
ここは三等三角点(点名:三ツ石)
標高は1,447.94mの場所だ。
運良く、積雪から三角点の頭が出ていた。
今年初の三角点タッチ!



さて、ここでシールを外すことにする。
シールを剥がす時に気づいた...
シール後方のエッジ部分が1cmほど切れている。
きっと石か木を踏んだのかと?
シール(Gecko)を修理してからトラブル続きだ...
▲12:05 覘標の台 下山
さて、ここからは滑走となる。
元来たルートへ戻るように、東斜面を滑走した。
東斜面は滑り易い雪質だった。

南方面のその奥に三ツ石山頂を眺める。

滑走に適したオープンバーンはあっという間に終了。

その後は暫く平坦な道のりである。
シールを貼るまでもないが、少々の登りもあり...
「少々」でもシール無しの登りは体力を使う。

緩斜面でもフワフワの雪は滑りが楽しい。
アオトドを掻い潜って滑る。

ある程度滑り、登りのトレースへと合流した。
さて、登り時に「滑りが楽しそう~」と思っていたあの斜面へ戻って来た。
風の流れで創られた雪の波を利用して相方は飛ぶ。


上質パウダー。

イイ斜面はあっという間に滑り降りてしまう。
ここを下りると、小ピークまでは短い区間だが登りになる。
シールを貼って登ることにした。
服の中にシールを入れておいたので、着いた粉雪も融けて貼り付きが良かった。
少々登っては小ピークで再びシールを剥がす。
ここからはもうシールは要らない。
奥産道の上部の樹林へ戻って来た。
針葉樹林から変わって斜面には藪もあり...
樹林密度の低い場所を選んで斜面滑走!


滑りは安全第一で!


▲13:00 奥産道
無事、奥産道へと戻って来た。
そのまま、奥産道を滑って下る。
せっかくここまで来たので、ちょっと上のトラス橋へも行ってみるんだったな...
下りの奥産道も平らなだけにちょっと歩きが面倒だな。(小畚橋の辺り)
それでも15分程度で閉鎖ゲートまで戻ることが出来た。

▲13:15 登山口
無事下山、お疲れさんでした。
今日の奥産道は我々2人のトレースのみだった。
源太ヶ岳へもここからは誰も入らなかったようだな。
先ずは今回のトレースを振り返る。

源太ヶ岳の樹林内と異なり、滑りに適した斜面は長くは続かない。
ところどころに平坦な場所が交じるといった感じである。
それでも初めてのルート。
景色が新鮮で、ハイクも飽きずに楽しむことが出来た。
何と言っても樹林外で天気が回復してくれたことが幸い。
厳冬期の三ツ石山であの絶景を味わえたことは嬉しい限り。
では、また山で!
(完)

この記事へのコメント
今日は。
奥産道と言うんですか?雪の無いときに車で少し行きました。そこは樹海ラインのスタートでもありますよね。
途中に下倉スキー場がありました。夏行くとゲレンデを横切ってるというか?スキー場のコースが道を跨いでるとかですよね。
下倉スキー場からは八幡平レストランですか?大きな駐車場までは今は行けないんでしょうね。歩けば別ですkが。
(^0^)
奥産道と言うんですか?雪の無いときに車で少し行きました。そこは樹海ラインのスタートでもありますよね。
途中に下倉スキー場がありました。夏行くとゲレンデを横切ってるというか?スキー場のコースが道を跨いでるとかですよね。
下倉スキー場からは八幡平レストランですか?大きな駐車場までは今は行けないんでしょうね。歩けば別ですkが。
(^0^)
Posted by isam at 2016年02月11日 21:32
こんばんは。
山頂であと10分、いや、あと5分待てばよかったかな?
でも風が冷たくて、限界でした。
反対側から見る三ツ石とミニ樹氷群も、なかなかの絶景だと思いました。
さて、週末は雨が降りそうだし、2/11が樹氷鑑賞のベストチャンスだったんのでは?
山頂であと10分、いや、あと5分待てばよかったかな?
でも風が冷たくて、限界でした。
反対側から見る三ツ石とミニ樹氷群も、なかなかの絶景だと思いました。
さて、週末は雨が降りそうだし、2/11が樹氷鑑賞のベストチャンスだったんのでは?
Posted by 緑茶 at 2016年02月12日 23:16
▼isamさん
こんにちは!
はい、今回はその奥産道から登りましたよ。
樹海ライン~八幡平までも冬季閉鎖ですね。
今ころは樹海ラインの一部が下倉スキー場のゲレンデになってます...
こんにちは!
はい、今回はその奥産道から登りましたよ。
樹海ライン~八幡平までも冬季閉鎖ですね。
今ころは樹海ラインの一部が下倉スキー場のゲレンデになってます...
Posted by PALOMON at 2016年02月13日 09:21
at 2016年02月13日 09:21
 at 2016年02月13日 09:21
at 2016年02月13日 09:21▼緑茶さん
こんにちは!
何か風がうまく防げなかったので、下山はしょうがなかったですね。
北側から眺める三ツ石山は雄大に感じられます。
八幡平のモンスターは例年に比べると痩せていましたが、やはり見応えあり、時間をかけて行ってよかったと思えますね!
こんにちは!
何か風がうまく防げなかったので、下山はしょうがなかったですね。
北側から眺める三ツ石山は雄大に感じられます。
八幡平のモンスターは例年に比べると痩せていましたが、やはり見応えあり、時間をかけて行ってよかったと思えますね!
Posted by PALOMON at 2016年02月13日 09:26
at 2016年02月13日 09:26
 at 2016年02月13日 09:26
at 2016年02月13日 09:26