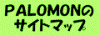2018年03月17日
和賀山塊-スキー縦走
日程:2018年03月17日(土) 日帰り
天候:曇

▲高下岳(こうげだけ)
岩手県(西和賀町)
標高: 1,322.2m
(地理院地図はこちら)
▲根菅岳(ねすがだけ)
岩手県(西和賀町)
標高: 1,345m
(地理院地図はこちら)
▲大荒沢岳(おおあらさわだけ)
岩手県(西和賀町)・秋田県(大仙市)
標高: 1,312.8m
(地理院地図はこちら)
▲沢尻岳(さわじりだけ)
岩手県(西和賀町)
標高: 1,260.0m
(地理院地図はこちら)
<ルート>
◎7:10 銀河高原ビール工場 ~ 8:10 高下岳登山口 ~ ▲10:50 高下岳 ~ ▲11:55 根菅岳 ~
▲13:20 大荒沢岳 ~ ▲14:05 沢尻岳 ~ 15:05 郡界分岐 ~ 15:40 沢尻岳登山口 ~ ◎16:20 貝沢集落
<関連記事>
2017年03月26日 大荒沢岳~羽後朝日岳-山スキー
2016年09月03日 高下岳~大荒沢岳~沢尻岳-縦走
2016年03月26日 大荒沢岳~羽後朝日岳-山スキー
2012年10月20日 和賀岳-登山
和賀山塊の4座!スキー縦走へ挑んでみた。
今季はなかなか山スキーへ出かけられず...気づけばもう3月中旬だ。
残りの時期、少しでも雪山を楽しまなければ!
今回ご一緒するのは地元山岳会のタラさんとSさん。
3名でのスキー山行である。
向かうは高下岳、根菅岳、大荒沢岳、沢尻岳、4座の縦走ルート。
以前はこのルートを夏に歩いたが、雪山もスキーで歩いてみたいルートだった。
冬場は積雪のため登山口まで車で行けないため林道歩きも強いられる。
総距離は18km。累積標高差は2,900mと歩きがいがあるルートだ。

◎7:10 銀河高原ビール工場
岩手の地ビールでお馴染みの銀河高原ビール。
その工場付近の除雪最終点へ車を停めて入山準備を行う。
この先に広がる雪原へ向かってスタート。
始めに目指すのは、高下岳登山口である。
その途中、大荒沢川を渡渉しなければならない。
事前にその渡渉が難点だと言われていた。


雪原の向こうに白く輝いている山が第1ピークの高下岳だろう。
雪原から雑木林を突破すると大荒沢川が見えてくる。


3月に大雨が降り、その後も暖かい日が続いていたせいか?
川は予想より幅があり渕も深くなっていた。
渡渉点が見つからないまま進むと堰堤が見えてきた。
あそこの下はうまく渡れるのか?

僅かに残っていた積雪を踏んで堰堤の裏側へ移動する。
ここは崩れず、何とか3名とも通過できた。

次に堰堤に引っかかっていた倒木を利用して渡渉を試みた。
自分は最後に渡ったが、靴底がビブラムソールではないのでツルツル滑って怖かった。
まあ、なんとか渡渉も成功。

非常にスリリングな渡渉だった。
渡渉後は今までのアプローチから本格的な山行に入った。
やや急な沢の中を登っていく。
ここは大きな段差もありスキーを脱いで登る必要もあった。

▲08:10 高下岳登山口
この沢を登りきった辺りが現在通行止め中の林道最終地点だった。
高下岳の登山口である。

高下岳登山口からは夏道に沿って登高を続ける。
今年の残雪は多いわけだがブナの幹周りは雪が融けて穴となっている。
これを根開きともいうようだな。
ブナの幹は熱を発しているのか?
正に春の前兆である。

更に登っていくと雪庇が見えてきた。
先日の雨のせいか?
これから現れる雪庇の殆どは崩壊していた。

この様な雪庇の上部には新雪で隠れた割れ目が存在している。
落ちないように注意が必要だ。
ブナが綺麗な場所で休憩をとった。
現在地を確認したところ未だ3分の1程度しか登っていなかった。
この辺りのブナ林は密度も少なく滑走向きの斜面である。
樹林内の雪面のコンディションもとても良かった。



樹林帯で視界が開ける場所があった。
そこから下界を眺める。
下界の天気は良さそうだ。青空が見えている。(逆に上部は曇り空だった...)

登高を続けるとブナ林から一転、ダケカンバ林へと変わっていく。
森林限界が近づいてきたということだ。

そして樹林帯を抜けた。
樹林外は風があって寒い...
今日はもっと天気が良く暖かい山行を想定していたのだが...

斜面へ取りつくが、気温が低いためガリガリのアイスバーンだった。
その上に若干降った新雪が乗っている感じだ。
新雪部分を使ってシールで我慢強く登り続ける。
新雪の無い部分はシールが滑ってうまく登れなかった。


難所を乗り越え尾根の上部へと出た。
青空は無いが見晴らしはまずまずといったところ。
高下岳(北峰)までもう直ぐだ。

▲10:50 高下岳
本日の第1ピークである高下岳(北峰)の山頂へ到着する。
和賀山塊最高峰の和賀岳(今日は行かない)へ続く峰を眺める。

山頂には長居せず...
風の弱い鞍部を目指して根菅岳方面へと移動開始。
ここでシールを剥がして滑走!
と行きたいところだが、今日の斜面の状況から判断し慎重に下りることを優先した。
スキーはザックへ括り(シートラーゲン)、高下岳山頂を慎重に下山する。


山頂直下の斜面は大きく割れていた。
安全優先で正解だった。
スキーを履き直し、シールは貼ったままで滑走と歩行の繰り返し。
尾根上の距離を稼ぐ。

風が落ち着いている場所を選んで休憩を挟んだ。
高下岳から大荒沢岳までは2時間以上かかるとのこと。
そのルート中間部に根菅岳が存在する。
根菅岳だが、地理院地図にはその名が記載されていない山である。
根菅岳は意外と大きな山だ。
(標高をみると本日ルートの4座のなかでもトップである。)
山頂直下ではイイ感じの青空が見られた。

▲11:55 根菅岳(ねすがだけ)
5時間弱で第2ピークの根菅岳までやって来た。
1年半前の夏時期に登った時はこの根菅岳の標識は存在しなかったな。

さて、根菅岳から次のピークの大荒沢岳を目指す。
最初はシールのまま滑走していたが、このガリガリ斜面をシールのまま滑走することは辛かった。
ここは自分だけシールを剥がした。
(後でシールの接着面を確認ところ、エッジ付近に損傷があった。)

他のメンバーはシール滑走でも差ほど疲れないとのことだった。
自分はシール滑走が苦手...腿が疲れて全然ダメだ...

先に鞍部まで滑り降り、シールを貼り直した。
その後は雪庇の痩せ尾根を通過することになる。


大きく割れた場所。
この辺りも雪面は凍っているので左右に落ちないように慎重に進む。

難所の雪庇地帯を通過すると、またまた難所が現れる。
大荒沢岳への急登である。
タラさんらは真っ先にシートラに切り替えた。
自分はここでシーアイゼン(クトー)を久しぶりに使ってみた。

(DIAMIR アクションアイゼン110)
ここは斜度があったのでシーアイゼンは歯が立たなかった。
二人に放されるだけなので途中で諦めシートラで追いかけた。
ここの急峻な登りは今日の山行の中で最も疲れた場所だ...

▲13:20 大荒沢岳
急登を終えた大荒沢岳ピークは清々しい。
第3ピークの大荒沢岳へ到着。
休憩をとりながら次の滑走へ向けてシールを剥がす。
(昨年、一昨年はこの大荒沢岳から朝日岳へ向かった。)


大荒沢岳からの大斜面を滑走する。
ここは意外と粉雪が吹き溜まっていた。
沢尻岳への鞍部までに小ピークがあるが、そのまま巻くように滑走を続ける。

大荒沢岳からの滑走はとても楽しかった。
鞍部から後ろを振り返る。
北側の斜面は結構崩れていた。
全層雪崩で笹が見えている箇所もあり。


再びシールを貼り最終ピークの沢尻岳を目指す。
今日の山行でシールを使うのはこれで最後になるだろう。

陽が照るとダケカンバの霧氷が見事に映った。


▲14:05 沢尻岳
縦走最終ピーク、沢尻岳へ登頂!
ここまで7時間、お疲れさんでした。

沢尻岳から最後の山塊景色を堪能する。
先程の大荒沢岳斜面にシュプールが良く見えていた。


今日の4ピーク全てに立派な山頂標識が作られていたな。
さて、沢尻岳からの滑走を開始。
下界は雫石方面に御所湖などがよく見えていた。
下界はイイ天気の様だ...

ここのオープンバーンは短めで、密あるダケカンバ林へと入っていく。

密あるダケカンバ林を過ぎるとブナ林へ入っていく。
この辺りは暫く平地となりシール無しでは頑張って歩かないといけない。
郡界分岐付近から斜度のあるブナ林になる。
ここのツリーランが本日最後の楽しみとなる。
流石にパウダーとはいかないが、雪も未だ重くなく滑り易かった。


最後の最後で樹林の滑りを楽しんだわけだが、蓄積した脚の疲労でちょっと雑な滑りとなった。
そのまま尾根沿いに滑っていくと、いつも通り途中で雪が途切れる。
やせた場所で、ここだけはいつも板を脱ぐことになる。

板を脱ぐのは一瞬の区間である。
板を履きなおして残る雪面を沢尻岳登山口まで一気に滑走した。
今日は登山口を過ぎても尚、林道の渡渉点までを滑走することが出来とても楽だった。


林道の渡渉を終えたら再びシール歩き。
この林道も30分くらいかかった。

▲16:20 貝沢集落
帰ってきた。
何だかんだで今日は9時間近い長めの山行となった。
取り敢えず無事下山、お疲れ様でした。

今季は山スキーがあまり出来ておらず体力も筋力もダラダラ状態だ。
1週間前に東栗駒山へ軽く登り、その際も靴擦れするなど...
今回のロングツアーはほんと疲労困憊といった感じ。
まあ、冬季にスキーで歩いてみたいルートだったので、達成できたことが何よりだ。
同行していただいた2人には感謝。
今回のルートは下記の通り。
昨年と一昨年に貝沢集落から羽後朝日岳までをピストンしたが、
今回と比較し距離は1km長かったが、累積標高差は1,180m程で同じくらいだった。

あっという間の3月。
残る残雪期、大いに山スキーを楽しみたい。
では、また山で!
(完)
残りの時期、少しでも雪山を楽しまなければ!
今回ご一緒するのは地元山岳会のタラさんとSさん。
3名でのスキー山行である。
向かうは高下岳、根菅岳、大荒沢岳、沢尻岳、4座の縦走ルート。
以前はこのルートを夏に歩いたが、雪山もスキーで歩いてみたいルートだった。
冬場は積雪のため登山口まで車で行けないため林道歩きも強いられる。
総距離は18km。累積標高差は2,900mと歩きがいがあるルートだ。

◎7:10 銀河高原ビール工場
岩手の地ビールでお馴染みの銀河高原ビール。
その工場付近の除雪最終点へ車を停めて入山準備を行う。
この先に広がる雪原へ向かってスタート。
始めに目指すのは、高下岳登山口である。
その途中、大荒沢川を渡渉しなければならない。
事前にその渡渉が難点だと言われていた。


雪原の向こうに白く輝いている山が第1ピークの高下岳だろう。
雪原から雑木林を突破すると大荒沢川が見えてくる。


3月に大雨が降り、その後も暖かい日が続いていたせいか?
川は予想より幅があり渕も深くなっていた。
渡渉点が見つからないまま進むと堰堤が見えてきた。
あそこの下はうまく渡れるのか?

僅かに残っていた積雪を踏んで堰堤の裏側へ移動する。
ここは崩れず、何とか3名とも通過できた。

次に堰堤に引っかかっていた倒木を利用して渡渉を試みた。
自分は最後に渡ったが、靴底がビブラムソールではないのでツルツル滑って怖かった。
まあ、なんとか渡渉も成功。

非常にスリリングな渡渉だった。
渡渉後は今までのアプローチから本格的な山行に入った。
やや急な沢の中を登っていく。
ここは大きな段差もありスキーを脱いで登る必要もあった。

▲08:10 高下岳登山口
この沢を登りきった辺りが現在通行止め中の林道最終地点だった。
高下岳の登山口である。

高下岳登山口からは夏道に沿って登高を続ける。
今年の残雪は多いわけだがブナの幹周りは雪が融けて穴となっている。
これを根開きともいうようだな。
ブナの幹は熱を発しているのか?
正に春の前兆である。

更に登っていくと雪庇が見えてきた。
先日の雨のせいか?
これから現れる雪庇の殆どは崩壊していた。

この様な雪庇の上部には新雪で隠れた割れ目が存在している。
落ちないように注意が必要だ。
ブナが綺麗な場所で休憩をとった。
現在地を確認したところ未だ3分の1程度しか登っていなかった。
この辺りのブナ林は密度も少なく滑走向きの斜面である。
樹林内の雪面のコンディションもとても良かった。



樹林帯で視界が開ける場所があった。
そこから下界を眺める。
下界の天気は良さそうだ。青空が見えている。(逆に上部は曇り空だった...)

登高を続けるとブナ林から一転、ダケカンバ林へと変わっていく。
森林限界が近づいてきたということだ。

そして樹林帯を抜けた。
樹林外は風があって寒い...
今日はもっと天気が良く暖かい山行を想定していたのだが...

斜面へ取りつくが、気温が低いためガリガリのアイスバーンだった。
その上に若干降った新雪が乗っている感じだ。
新雪部分を使ってシールで我慢強く登り続ける。
新雪の無い部分はシールが滑ってうまく登れなかった。


難所を乗り越え尾根の上部へと出た。
青空は無いが見晴らしはまずまずといったところ。
高下岳(北峰)までもう直ぐだ。

▲10:50 高下岳
本日の第1ピークである高下岳(北峰)の山頂へ到着する。
和賀山塊最高峰の和賀岳(今日は行かない)へ続く峰を眺める。

山頂には長居せず...
風の弱い鞍部を目指して根菅岳方面へと移動開始。
ここでシールを剥がして滑走!
と行きたいところだが、今日の斜面の状況から判断し慎重に下りることを優先した。
スキーはザックへ括り(シートラーゲン)、高下岳山頂を慎重に下山する。


山頂直下の斜面は大きく割れていた。
安全優先で正解だった。
スキーを履き直し、シールは貼ったままで滑走と歩行の繰り返し。
尾根上の距離を稼ぐ。

風が落ち着いている場所を選んで休憩を挟んだ。
高下岳から大荒沢岳までは2時間以上かかるとのこと。
そのルート中間部に根菅岳が存在する。
根菅岳だが、地理院地図にはその名が記載されていない山である。
根菅岳は意外と大きな山だ。
(標高をみると本日ルートの4座のなかでもトップである。)
山頂直下ではイイ感じの青空が見られた。

▲11:55 根菅岳(ねすがだけ)
5時間弱で第2ピークの根菅岳までやって来た。
1年半前の夏時期に登った時はこの根菅岳の標識は存在しなかったな。

さて、根菅岳から次のピークの大荒沢岳を目指す。
最初はシールのまま滑走していたが、このガリガリ斜面をシールのまま滑走することは辛かった。
ここは自分だけシールを剥がした。
(後でシールの接着面を確認ところ、エッジ付近に損傷があった。)

他のメンバーはシール滑走でも差ほど疲れないとのことだった。
自分はシール滑走が苦手...腿が疲れて全然ダメだ...

先に鞍部まで滑り降り、シールを貼り直した。
その後は雪庇の痩せ尾根を通過することになる。


大きく割れた場所。
この辺りも雪面は凍っているので左右に落ちないように慎重に進む。

難所の雪庇地帯を通過すると、またまた難所が現れる。
大荒沢岳への急登である。
タラさんらは真っ先にシートラに切り替えた。
自分はここでシーアイゼン(クトー)を久しぶりに使ってみた。

(DIAMIR アクションアイゼン110)
 DIAMIR(ディアミール) アクションアイゼン 110mm FR42502 |
ここは斜度があったのでシーアイゼンは歯が立たなかった。
二人に放されるだけなので途中で諦めシートラで追いかけた。
ここの急峻な登りは今日の山行の中で最も疲れた場所だ...

▲13:20 大荒沢岳
急登を終えた大荒沢岳ピークは清々しい。
第3ピークの大荒沢岳へ到着。
休憩をとりながら次の滑走へ向けてシールを剥がす。
(昨年、一昨年はこの大荒沢岳から朝日岳へ向かった。)


大荒沢岳からの大斜面を滑走する。
ここは意外と粉雪が吹き溜まっていた。
沢尻岳への鞍部までに小ピークがあるが、そのまま巻くように滑走を続ける。

大荒沢岳からの滑走はとても楽しかった。
鞍部から後ろを振り返る。
北側の斜面は結構崩れていた。
全層雪崩で笹が見えている箇所もあり。


再びシールを貼り最終ピークの沢尻岳を目指す。
今日の山行でシールを使うのはこれで最後になるだろう。

陽が照るとダケカンバの霧氷が見事に映った。


▲14:05 沢尻岳
縦走最終ピーク、沢尻岳へ登頂!
ここまで7時間、お疲れさんでした。

沢尻岳から最後の山塊景色を堪能する。
先程の大荒沢岳斜面にシュプールが良く見えていた。


今日の4ピーク全てに立派な山頂標識が作られていたな。
さて、沢尻岳からの滑走を開始。
下界は雫石方面に御所湖などがよく見えていた。
下界はイイ天気の様だ...

ここのオープンバーンは短めで、密あるダケカンバ林へと入っていく。

密あるダケカンバ林を過ぎるとブナ林へ入っていく。
この辺りは暫く平地となりシール無しでは頑張って歩かないといけない。
郡界分岐付近から斜度のあるブナ林になる。
ここのツリーランが本日最後の楽しみとなる。
流石にパウダーとはいかないが、雪も未だ重くなく滑り易かった。


最後の最後で樹林の滑りを楽しんだわけだが、蓄積した脚の疲労でちょっと雑な滑りとなった。
そのまま尾根沿いに滑っていくと、いつも通り途中で雪が途切れる。
やせた場所で、ここだけはいつも板を脱ぐことになる。

板を脱ぐのは一瞬の区間である。
板を履きなおして残る雪面を沢尻岳登山口まで一気に滑走した。
今日は登山口を過ぎても尚、林道の渡渉点までを滑走することが出来とても楽だった。


林道の渡渉を終えたら再びシール歩き。
この林道も30分くらいかかった。

▲16:20 貝沢集落
帰ってきた。
何だかんだで今日は9時間近い長めの山行となった。
取り敢えず無事下山、お疲れ様でした。

今季は山スキーがあまり出来ておらず体力も筋力もダラダラ状態だ。
1週間前に東栗駒山へ軽く登り、その際も靴擦れするなど...
今回のロングツアーはほんと疲労困憊といった感じ。
まあ、冬季にスキーで歩いてみたいルートだったので、達成できたことが何よりだ。
同行していただいた2人には感謝。
今回のルートは下記の通り。
昨年と一昨年に貝沢集落から羽後朝日岳までをピストンしたが、
今回と比較し距離は1km長かったが、累積標高差は1,180m程で同じくらいだった。

あっという間の3月。
残る残雪期、大いに山スキーを楽しみたい。
では、また山で!
(完)
この記事へのコメント
いつも、ヤマレコへの拍手ありがとうございます。m(__)m
PALOMINOさんの山旅を拝見するの楽しみにしております。
PALOMINOさんの山旅を拝見するの楽しみにしております。
Posted by gikyu at 2018年03月26日 23:14
▼gikyuさん
こんばんは!
こちらこそ、いつも楽しくヤマレコを拝見させて頂いてます。
今季は残雪も多いので5月末までは滑りを楽しめそうですね!
こんばんは!
こちらこそ、いつも楽しくヤマレコを拝見させて頂いてます。
今季は残雪も多いので5月末までは滑りを楽しめそうですね!
Posted by PALOMON at 2018年03月27日 20:03
at 2018年03月27日 20:03
 at 2018年03月27日 20:03
at 2018年03月27日 20:03お久し振りです。
いつぞや鉛温泉でご一緒したものです。
イヤースゲーとこいってますね
今期からテックに変えましたがから増量の方が遥かに多く意味ないじゃ~ん
スキー場からのアプローチと八甲田くらいで今期は終えちゃいました~
来期は栗駒いくぞ~
いつぞや鉛温泉でご一緒したものです。
イヤースゲーとこいってますね
今期からテックに変えましたがから増量の方が遥かに多く意味ないじゃ~ん
スキー場からのアプローチと八甲田くらいで今期は終えちゃいました~
来期は栗駒いくぞ~
Posted by オレンジのT at 2018年07月21日 16:56
▼オレンジのTさん
こんばんは、お久しぶりです!
このルートは滑り重視ではなく「歩き重視」です。
ツアーってやつですね。
TLTですか!私も興味あります。
でも高いですよね(^-^;
次の板を購入する際にはTLTを付けようと思います~!
栗駒は練習にもイイ山です。
こんばんは、お久しぶりです!
このルートは滑り重視ではなく「歩き重視」です。
ツアーってやつですね。
TLTですか!私も興味あります。
でも高いですよね(^-^;
次の板を購入する際にはTLTを付けようと思います~!
栗駒は練習にもイイ山です。
Posted by PALOMON at 2018年07月21日 21:51
at 2018年07月21日 21:51
 at 2018年07月21日 21:51
at 2018年07月21日 21:51滑り重視なんで後ろがアルペンタイプ‼
装備全部で今までの半分以下14キロ→7キロ
テックならサロモンが出しますよ。これもアルペンタイプですが、フロントが合わせやすいのが特徴です。
まぁ、4時帰りの滑り重視ツアーでゼハー言ってるようじゃ体重落とせって話ですけどね
装備全部で今までの半分以下14キロ→7キロ
テックならサロモンが出しますよ。これもアルペンタイプですが、フロントが合わせやすいのが特徴です。
まぁ、4時帰りの滑り重視ツアーでゼハー言ってるようじゃ体重落とせって話ですけどね
Posted by オレンジのT at 2018年07月25日 19:07
▼オレンジのT さん
いろんなタイプのビンディングがあるんですね~
軽量なものには興味がありますよ。
現在使用中の板もディアミールも、年数が経っているので新たな道具も検討したいところです。
いろんなタイプのビンディングがあるんですね~
軽量なものには興味がありますよ。
現在使用中の板もディアミールも、年数が経っているので新たな道具も検討したいところです。
Posted by PALOMON at 2018年07月27日 08:10
at 2018年07月27日 08:10
 at 2018年07月27日 08:10
at 2018年07月27日 08:10