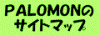2014年11月09日
黒森山(乙部三山)-登山

日程:2014年11月8日(土) 日帰り
天気:晴

▲黒森山(くろもりやま)
標高:836.7m
岩手県 盛岡市
万寿坑跡・虫壁林道より
<地理院地図はこちら>
<ルート>
万寿坑跡(駐車場)~虫壁林道~
ガロの滝(分岐点)~深沢コース~
▲黒森山~峠コース~駐車場
11月ともなれば私的に登山もシーズンオフに入ると言ったところだ。
11~12月で体力が結構落ちてしまう。 (さっぱり運動せずで...)
しかし今年は11~12月も出来るだけ登山を継続したいと思っている。
今回は夕方から用事があるため、午前中で山行き可能な山を選択してみた。
紅葉も終わり、高い山には雪が積もっている。
この時期の登山に相応しそうな里山を選択してみた。
先日購入した阿部さんの本、岩手の山150を参考にさせて頂いた。
盛岡市にある乙部三山のひとつ、黒森山を選択した。
今回初めて登る訳だが、山仲間から里山としての評価が高かった山のひとつである。
始めは沢沿いを歩き、そして尾根へ出る。
山頂へたどり着けば、そこに広がる景色はとても良く岩手山の眺めもイイらしい!
登山口は万寿抗跡のある虫壁コースから入山する。
その他のコースは初めてだと分かり難い(遭難しそう...)とのアドバイスも頂いていた。
まずは万寿坑跡の駐車場に車を停める。

私の他に車が1台入り、単独の方が登山準備を始めていた。
話を聞くと地元の方で何度か登っているとのことだ。
初めてで不安もあるので、有り難くその方の後ろを歩かせて頂いた。
これらのオブジェを横目に登山道へと向かう。

聞いた話では、ここは岩手大学美術科のアトリエらしい。




▲8:45 登山道入口
黒森山登山道入口。
登山は歓迎とのことだ。
ここから暫く緩やかな虫壁林道を歩くことになる。

虫壁林道は車両通行止め。
登山口から最初の橋を越えた辺りに車両止のチェーンが張られている。
チェーンを跨いでその先へと向かった。

落ち葉の積もった林道を進む。
乾いた色々な木の葉が、それはいっぱい積もっていた。
深さもありフカフカの道。 軽快に歩くことが出来る。

大きな葉っぱ2種類をゲット。

林道脇には綺麗な沢が暫く流れていた。
「鍋倉の滝」、「いただきの渓流」、と書かれた看板がこの沢沿いに見られた。

▲9:15 姥湖水明神(うばこすいみょうじん)
暫く歩いて来ると林道脇に水場を発見できる。
ここに柄杓が置かれていたので、飲めるのであろうと判断する。
柄杓にて流れ出る水を頂いた。 うん、とても美味い水だ!



(山の湧水でまたまた少し若返る...)
深く積もった枯れ葉の中には落石なども隠れている。
それはちょっと注意!

▲9:25 ガロの滝
さて、虫壁林道を歩くこと40分程。 「ガロの滝」までやってきた。


ここの木の橋は落ち葉で埋もれていた。
看板にも書かれているが、山側を踏み外さないように慎重に渡ろう。

そして徒渉地点も多くの落ち葉で埋もれていた。
足元に気付かないと沢に足を落としてしまうだろう。
と言うことで、ここは一気に飛び越える! (気をつけて渡りましょう。)

ここが「深沢コース」と「峠コース」の分岐点である。
先行者が深沢コースを登って行ったので、私もその跡を追うことにした。



この辺の登山道はちょっと分かり難い。
枝にあるピンクリボンを頼りに登って行く。
その後も幾つか深沢の徒渉を重ねていく。
矢印などの看板が多く設置されていたので迷うことなく安心させられた。

深沢に沿って登ってきたが、途中から進路は尾根へと向かった。
短めの急登を終えて尾根にたどり着いた。

ここで聞こえたメール着信音で気がついた。
結構な山奥ではあるが、この辺りは携帯電波が通っているんだ。
今日の夕方から行われるとある会のやり取りをメールで交わしながら歩いた。
尾根歩きは沢歩きとは雰囲気が違っていた。
次第に松の樹が多くなっていった。
山頂まであと○○○メートル、という看板が随所に見られる。
重石コースへの分岐点まで登ってきた。
何れは重石コースからも登ってみたいと思う。
しかし、どれだけ分かり難い道なのだろうか...?
さあ、ここまで来れば山頂も間近だ。

▲10:15 黒森山山頂
1時間半程で無事登頂。 おめでとう!
今までは樹林内だったが、山頂だけ景色が開けていた。
そこにとても良い景色が広がっている。

先ずは三角点へタッチ!
赤く染められた石柱は一等三角点だった。
黒森山は気になっていた里山のひとつ。
低山ながら登頂には十分満足する。



先行して頂いた方は登って来た深沢コースを戻るとのこと。
峠コースは藪なので、そちらへは下ったことがないとの事だった。
ここで別れを告げる。
黒森山の山頂を独り占めして、雄大な展望を楽しんだ。
乙部三山の朝島山(左)と鬼ヶ瀬山(右)を見下ろす。

その真ん中にドンと聳える岩手山。

姫神山も良く見えていた。

紫波三山。 そのバックに薄らと見えるのは和賀山塊だろう。

天気に恵まれ青空の下、景色は最高!
そしてこの時期にしてはとても暖かい。 それはいい!
山頂の木製ベンチでコーヒーを淹れてちょっとのんびり...
一段と美味しいコーヒーで寛ぎのひと時。

こちらは旧都南村の看板。
岩手山の標高も大分古い数値である...

▲10:40 下山開始
さて、どちらに下るか迷ったが、下山は別の「峠コース」に決めた。
先ほどの方は藪を心配していた。
しかし、この時期は葉が落ちてしまっているので藪は心配なかった。
コース沿いには矢印などの看板も多く備えられ、これなら迷うこともなさそうだ。
山頂から少し下ったところに噂の石塁を発見した。
左側に暫くこの石塁が続いた。
何の石塁か? 気になっていたが...
これは盛岡市と紫波町の境を表しているのだと予想する。

ずっと下りかと思えば、若干の登り返しもある。
黒森山を予習した時に、このルートは熊の糞が多いとの情報を得ていた。
確かにこの辺りには熊が出てきそう...
そう考えると、その中を1人で歩くのは何とも心細い...
再び石塁が続く。
今度はこの石塁の上を歩いた。 (その様な登山道になっている。)
この坂には「蛇紋坂」という名がついていた。

▲11:10 峠(弁当場)分岐点
弁当を食べる場所に適しているのかな?
熊を恐れていたわけではないが、ここまで下りは小走りに。
山頂から30分程度で下りてきた。

後は再び落ち葉が敷き詰められた虫壁林道を戻って行くのみだ。
▲11:20 ガロの滝
峠からガロの滝までは10分程度で戻ってくる。
あとは元来た道を戻るだけ。
深い枯れ葉ロードを尚も小走りに下った。
途中、水場の姥湖水明神で水を飲む。
やっぱりこの山水が美味い。

最後には先ほどの登山者に追いついた。
そして峠コースの状況を伝えた。
峠コースは石塁が不思議さを出していて面白かった。
藪が心配な時期は登りに利用した方が道が分かりやすいだろう。
▲11:40 虫壁登山口
下山はやや早めに歩いて、山頂から1時間程で虫壁林道から脱出した。
再びあのオブジェロードを歩いて駐車場へと無事下山。
今日歩いた軌跡は下記の通り。

11~12月、登山はまだまだ続けたい。
今回の様に低山をサラリと歩くのもイイものだ。
天気が良ければお昼に合わせて山でのランチも捨てがたいな。
阿部さんの「岩手の山150」から次なる低山を選出しよう!
ではまた山で。
(完)

THE NORTH FACE(ザ・ノースフェイス) HOT TROUSERS Men’s

THE NORTH FACE(ザ・ノースフェイス) WARM TROUSERS Men’s

シマノ(SHIMANO) IN-025K ブレスハイパー+度 ストレッチアンダータイツ(極厚タイプ)
この時期の登山に相応しそうな里山を選択してみた。
先日購入した阿部さんの本、岩手の山150を参考にさせて頂いた。
盛岡市にある乙部三山のひとつ、黒森山を選択した。
今回初めて登る訳だが、山仲間から里山としての評価が高かった山のひとつである。
始めは沢沿いを歩き、そして尾根へ出る。
山頂へたどり着けば、そこに広がる景色はとても良く岩手山の眺めもイイらしい!
登山口は万寿抗跡のある虫壁コースから入山する。
その他のコースは初めてだと分かり難い(遭難しそう...)とのアドバイスも頂いていた。
まずは万寿坑跡の駐車場に車を停める。

私の他に車が1台入り、単独の方が登山準備を始めていた。
話を聞くと地元の方で何度か登っているとのことだ。
初めてで不安もあるので、有り難くその方の後ろを歩かせて頂いた。
これらのオブジェを横目に登山道へと向かう。

聞いた話では、ここは岩手大学美術科のアトリエらしい。




▲8:45 登山道入口
黒森山登山道入口。
登山は歓迎とのことだ。
ここから暫く緩やかな虫壁林道を歩くことになる。

虫壁林道は車両通行止め。
登山口から最初の橋を越えた辺りに車両止のチェーンが張られている。
チェーンを跨いでその先へと向かった。

落ち葉の積もった林道を進む。
乾いた色々な木の葉が、それはいっぱい積もっていた。
深さもありフカフカの道。 軽快に歩くことが出来る。

大きな葉っぱ2種類をゲット。

林道脇には綺麗な沢が暫く流れていた。
「鍋倉の滝」、「いただきの渓流」、と書かれた看板がこの沢沿いに見られた。

▲9:15 姥湖水明神(うばこすいみょうじん)
暫く歩いて来ると林道脇に水場を発見できる。
ここに柄杓が置かれていたので、飲めるのであろうと判断する。
柄杓にて流れ出る水を頂いた。 うん、とても美味い水だ!



(山の湧水でまたまた少し若返る...)
深く積もった枯れ葉の中には落石なども隠れている。
それはちょっと注意!

▲9:25 ガロの滝
さて、虫壁林道を歩くこと40分程。 「ガロの滝」までやってきた。


ここの木の橋は落ち葉で埋もれていた。
看板にも書かれているが、山側を踏み外さないように慎重に渡ろう。

そして徒渉地点も多くの落ち葉で埋もれていた。
足元に気付かないと沢に足を落としてしまうだろう。
と言うことで、ここは一気に飛び越える! (気をつけて渡りましょう。)

ここが「深沢コース」と「峠コース」の分岐点である。
先行者が深沢コースを登って行ったので、私もその跡を追うことにした。



この辺の登山道はちょっと分かり難い。
枝にあるピンクリボンを頼りに登って行く。
その後も幾つか深沢の徒渉を重ねていく。
矢印などの看板が多く設置されていたので迷うことなく安心させられた。

深沢に沿って登ってきたが、途中から進路は尾根へと向かった。
短めの急登を終えて尾根にたどり着いた。

ここで聞こえたメール着信音で気がついた。
結構な山奥ではあるが、この辺りは携帯電波が通っているんだ。
今日の夕方から行われるとある会のやり取りをメールで交わしながら歩いた。
尾根歩きは沢歩きとは雰囲気が違っていた。
次第に松の樹が多くなっていった。
山頂まであと○○○メートル、という看板が随所に見られる。
重石コースへの分岐点まで登ってきた。
何れは重石コースからも登ってみたいと思う。
しかし、どれだけ分かり難い道なのだろうか...?
さあ、ここまで来れば山頂も間近だ。

▲10:15 黒森山山頂
1時間半程で無事登頂。 おめでとう!
今までは樹林内だったが、山頂だけ景色が開けていた。
そこにとても良い景色が広がっている。

先ずは三角点へタッチ!
赤く染められた石柱は一等三角点だった。
黒森山は気になっていた里山のひとつ。
低山ながら登頂には十分満足する。



先行して頂いた方は登って来た深沢コースを戻るとのこと。
峠コースは藪なので、そちらへは下ったことがないとの事だった。
ここで別れを告げる。
黒森山の山頂を独り占めして、雄大な展望を楽しんだ。
乙部三山の朝島山(左)と鬼ヶ瀬山(右)を見下ろす。

その真ん中にドンと聳える岩手山。

姫神山も良く見えていた。

紫波三山。 そのバックに薄らと見えるのは和賀山塊だろう。

天気に恵まれ青空の下、景色は最高!
そしてこの時期にしてはとても暖かい。 それはいい!
山頂の木製ベンチでコーヒーを淹れてちょっとのんびり...
一段と美味しいコーヒーで寛ぎのひと時。

こちらは旧都南村の看板。
岩手山の標高も大分古い数値である...

▲10:40 下山開始
さて、どちらに下るか迷ったが、下山は別の「峠コース」に決めた。
先ほどの方は藪を心配していた。
しかし、この時期は葉が落ちてしまっているので藪は心配なかった。
コース沿いには矢印などの看板も多く備えられ、これなら迷うこともなさそうだ。
山頂から少し下ったところに噂の石塁を発見した。
左側に暫くこの石塁が続いた。
何の石塁か? 気になっていたが...
これは盛岡市と紫波町の境を表しているのだと予想する。

ずっと下りかと思えば、若干の登り返しもある。
黒森山を予習した時に、このルートは熊の糞が多いとの情報を得ていた。
確かにこの辺りには熊が出てきそう...
そう考えると、その中を1人で歩くのは何とも心細い...
再び石塁が続く。
今度はこの石塁の上を歩いた。 (その様な登山道になっている。)
この坂には「蛇紋坂」という名がついていた。

▲11:10 峠(弁当場)分岐点
弁当を食べる場所に適しているのかな?
熊を恐れていたわけではないが、ここまで下りは小走りに。
山頂から30分程度で下りてきた。

後は再び落ち葉が敷き詰められた虫壁林道を戻って行くのみだ。
▲11:20 ガロの滝
峠からガロの滝までは10分程度で戻ってくる。
あとは元来た道を戻るだけ。
深い枯れ葉ロードを尚も小走りに下った。
途中、水場の姥湖水明神で水を飲む。
やっぱりこの山水が美味い。

最後には先ほどの登山者に追いついた。
そして峠コースの状況を伝えた。
峠コースは石塁が不思議さを出していて面白かった。
藪が心配な時期は登りに利用した方が道が分かりやすいだろう。
▲11:40 虫壁登山口
下山はやや早めに歩いて、山頂から1時間程で虫壁林道から脱出した。
再びあのオブジェロードを歩いて駐車場へと無事下山。
今日歩いた軌跡は下記の通り。

11~12月、登山はまだまだ続けたい。
今回の様に低山をサラリと歩くのもイイものだ。
天気が良ければお昼に合わせて山でのランチも捨てがたいな。
阿部さんの「岩手の山150」から次なる低山を選出しよう!
ではまた山で。
(完)

THE NORTH FACE(ザ・ノースフェイス) HOT TROUSERS Men’s

THE NORTH FACE(ザ・ノースフェイス) WARM TROUSERS Men’s

シマノ(SHIMANO) IN-025K ブレスハイパー+度 ストレッチアンダータイツ(極厚タイプ)
Posted by PALOMON at 22:25│Comments(10)
│黒森山
この記事へのコメント
お疲れ様です。
では鬼ヶ瀬、朝島行かないと行けなくなりましたね(笑)
黒森は獣臭がすごかったと聞いてました(笑)
では鬼ヶ瀬、朝島行かないと行けなくなりましたね(笑)
黒森は獣臭がすごかったと聞いてました(笑)
Posted by 結斗パパ at 2014年11月10日 09:46
▼結斗パパさん
こんにちは。
乙部三山ですか~
時間があれば、黒森の後に朝島も登れますね。
やはり獣臭が?
でも、もう冬眠時期なのかな~?
こんにちは。
乙部三山ですか~
時間があれば、黒森の後に朝島も登れますね。
やはり獣臭が?
でも、もう冬眠時期なのかな~?
Posted by PALOMON at 2014年11月10日 12:45
at 2014年11月10日 12:45
 at 2014年11月10日 12:45
at 2014年11月10日 12:45黒森山、いいですよね。冬もいいですよ~。
鬼ヶ瀬、朝島はぜひセットでどうぞ!
葉っぱはやっぱり持ち帰ったんですか?
鬼ヶ瀬、朝島はぜひセットでどうぞ!
葉っぱはやっぱり持ち帰ったんですか?
Posted by けむけむ at 2014年11月10日 22:57
どこそこの三山というのは良くあるパターンですよね。
出羽三山、遠野三山、近くでは文字三山など。
岩手の三山とは余り言いませんが、無理して言えば、岩手山、早池峰山、須川岳かな?でも須川だと岳ですので栗駒山。無理があるでしょうかね。(^0^)
一関の三山だと、室根山、須川岳、あとひとつは、束稲山かな?
出羽三山、遠野三山、近くでは文字三山など。
岩手の三山とは余り言いませんが、無理して言えば、岩手山、早池峰山、須川岳かな?でも須川だと岳ですので栗駒山。無理があるでしょうかね。(^0^)
一関の三山だと、室根山、須川岳、あとひとつは、束稲山かな?
Posted by isam at 2014年11月10日 23:28
▼けむけむさん
こんにちは。
黒森山、沢沿いの登山道が気に入りました。
鬼ヶ瀬、朝島はセットですかっ!
2座くらいならと思ってましたが...
葉っぱは山頂のテーブルの上に置いてきましたよ~。
こんにちは。
黒森山、沢沿いの登山道が気に入りました。
鬼ヶ瀬、朝島はセットですかっ!
2座くらいならと思ってましたが...
葉っぱは山頂のテーブルの上に置いてきましたよ~。
Posted by PALOMON at 2014年11月11日 08:13
at 2014年11月11日 08:13
 at 2014年11月11日 08:13
at 2014年11月11日 08:13▼isamさん
こんにちは。
確かに三山っていろいろありますね。
乙部三山はマイナーで、鬼ヶ瀬山なんて何処って感じで...
文字三山とは聞いたことないです。
岩手だと、その他、夏油三山、志和三山ってのもありますね~
こんにちは。
確かに三山っていろいろありますね。
乙部三山はマイナーで、鬼ヶ瀬山なんて何処って感じで...
文字三山とは聞いたことないです。
岩手だと、その他、夏油三山、志和三山ってのもありますね~
Posted by PALOMON at 2014年11月11日 08:22
at 2014年11月11日 08:22
 at 2014年11月11日 08:22
at 2014年11月11日 08:2211月になると行ける山が限られますね。
私も仙台近郊の里山歩きしてますよ。
山にもようやく雪が積り始めたようですので
そろそろ板の出番ですね。
私も仙台近郊の里山歩きしてますよ。
山にもようやく雪が積り始めたようですので
そろそろ板の出番ですね。
Posted by sharizaka at 2014年11月15日 12:27
▼sharizakaさん
こんにちは。
初冬ですね。
今日は平地も雪、いよいよタイヤ交換です。
そんな中、里山歩きも楽しいですね。
さて、そろそろ板も取り出して、ワックスでも塗っておこうかな...
こんにちは。
初冬ですね。
今日は平地も雪、いよいよタイヤ交換です。
そんな中、里山歩きも楽しいですね。
さて、そろそろ板も取り出して、ワックスでも塗っておこうかな...
Posted by PALOMON at 2014年11月15日 19:18
at 2014年11月15日 19:18
 at 2014年11月15日 19:18
at 2014年11月15日 19:18黒森山の石は、紫波との境では無くて、父の話によると、むかしは、馬を使って伐採した木を運んだりしたそうで、馬が逃げないように石が積まれたものだとのこと。馬は大切な労働力だったそうです。
Posted by ジョリー at 2014年12月19日 23:43
▼ジョリーさん
こんにちは!
なるほど...
黒森山の石垣の謎、とても気になっていました。
あれだけの石を積むのも昔は重労働だったのでしょうね。
貴重な情報、ありがとうございます!
こんにちは!
なるほど...
黒森山の石垣の謎、とても気になっていました。
あれだけの石を積むのも昔は重労働だったのでしょうね。
貴重な情報、ありがとうございます!
Posted by PALOMON at 2014年12月20日 15:38
at 2014年12月20日 15:38
 at 2014年12月20日 15:38
at 2014年12月20日 15:38